中学生がゲーミングPCを買いたいって言ったら、親の反応も気になるし、そもそもお金はどうするの?って悩みますよね。
「中学生 ゲーミングpc お金」で調べてるあなたに、現実的なヒントを詰め込みました。
- 中学生のゲーミングpcのお金の現実と、購入までのリアルなステップ
- お金の貯め方と、実行しやすい節約術
- 親に反対されがちな理由と、納得してもらえる伝え方のコツ
- ゲームだけじゃない!プログラミングも学べる説得ポイント
中学生のゲーミングpcのお金の現実|まず知っておくべき基礎知識
中学生がゲーミングPCを手に入れたいと思ったとき、まず理解しておくべきは「費用」と「資金源」。この記事ではその現実を正確に伝えます。
- 中学生でもゲーミングPCは買える?購入のハードルとポイント
- 価格帯はどのくらいから?スペック別に目安を解説
- お金の「出どころ」は?親から?お小遣い?バイト?
- 親に不安視される理由とは
中学生でもゲーミングPCは買える?購入のハードルとポイント
正直に言いますと、中学生でもゲーミングPCを手に入れることはできると思います。
まず、予算面では「12万円〜16万円ほどが、BTO(注文制作型)ゲーミングPCの現実的な目安ライン」になっています 。
中学生の立場では決して軽い金額ではないけど、アルバイトやお年玉、お小遣いを積み立てて…という方法で、じっくり準備すれば十分可能です。
ただし、購入を目指す上で避けて通れないのがいくつかのハードルです。
まず一つめは、親の理解。親御さんから「中学生が買うものじゃない」「ゲームにのめり込んでしまうかも…」という反応をもらうことは、本当に多いです。
もう一つは、金銭面の責任感。単なる遊び道具じゃなくて、学習やプログラミング、動画編集など他の用途にもしっかり使うことを説明すると、OKしてもらいやすくなるんですよね。
さらに、スペックの適正判断も大事です。たとえば、Ryzen5+RTX 5060構成なら12万円台で揃うケースもあって、これは「価格と性能のバランス」の観点からも初心者には現実的なライン 。
リビング設置のデスクトップだとスペースも取るし、ノートだと144Hz対応モデルも増えていて場所も取らずスマートなので、用途に合わせて選ぶと良いですね。
価格帯はどのくらいから?スペック別に目安を解説
ゲーミングPCの価格は、用途や性能によって幅がありますが、日本の市場では以下のラインナップが目安になります。
- エントリーモデル(ライトユーザー向け)
- およそ10万円程度から購入可能。
- 軽めのゲームや基本的なタイトルなら問題なく動きます。
- ミドルモデル(快適なプレイを目指すなら)
- 20万円~30万円の価格帯が標準的。
- 人気タイトルを高画質で遊びたい場合、このあたりが現実的な選択肢です。
- スタンダードなBTOモデル
- 実際に国内でよく売れているBTOブランドでは、18〜20万円(税込・送料込み)程度が相場との声もあります。
また、ゲーミングPCをプレイ環境として整える場合、本体だけでなくモニターやキーボード、マウスなど一式を揃えると総額で20〜30万円程度かかることも覚えておいてください。
特にモニターは、144Hzなど高リフレッシュレート対応だとコストがプラスされます。
▼価格帯別のおすすめについて詳しいことはこちらの記事で紹介しています。
ゲーミングPCは5万以下で新品は買える?初心者向けおすすめモデルと選び方を徹底解説
ゲーミングpcは10万以下で中古で買える?プロが選ぶコスパ最強モデル5選
自作する?
「自作ってちょっと難しそう…」って思うかもしれませんが、実際には小中学生でもできるくらい組み立ては簡単なんです—いわばレゴや模型を作る感覚に近いんですよ 。
メリット
- コスパが良い:同じスペックのBTO(既製PC)より安く仕上がることが多いので、お小遣いや貯金を有効に使えます。
- カスタマイズ性も自由自在:好きなパーツを選べるので、好きな色や見た目にこだわれて、自分だけのPCになるのも楽しさの一つ。
- 将来のアップグレードや知識にもつながる:パーツ交換もラク、パソコンの仕組みや扱いに詳しくなるから、勉強にも役立つんです。
デメリット
- 知識や経験が必要:パーツの選び方や相性、組み立て方など、ある程度の理解や手順の確認が欠かせません。
- 保証やサポートが分かれる:トラブル時には自分で直す必要があるので、初心者だと対応が難しいと感じることもあります。
お金の「出どころ」は?親から?お小遣い?バイト?

中学生がゲーミングPCを手に入れるためには、お金の“出どころ”を現実的に理解することが大切です。以下に、主な資金源を整理してみました。
① お小遣い:月いくらもらってる?
日本の中学生がもらっているお小遣いの平均は、家庭ごとに差がありますが、おおよそ月 2,500円~3,400円前後という調査結果が出ています。
例えば、PR TIMESによる調査では平均 3,390円と報告されており、金融広報中央委員会などの調査では 2,500円程度というデータもあります。
学年が上がるほど金額も増える傾向があり、中学1年生は約 1,380円、2年生は 1,568円、3年生では 2,112円というデータも確認できます。
ただし、家庭によってはお小遣い制度自体を採用していない例もあり、家族内で話し合って決めているケースも多いです。
② 親や祖父母からの支援も頼りに
お小遣い以外の資金源として、親や祖父母から臨時に援助を受けるケースもあります。金融広報中央委員会の調査では、中学生のお小遣いの出どころとして「親」が約92.3%、「祖父母」が約34.3%と報告されています。
家族の中でお金の出し方に柔軟性があるかどうかも、重要なポイントになりますね。
③ アルバイト・バイト収入は“基本NG”
中学生のアルバイトについて、日本の法律では原則できないとされています。
労働基準法第56条により、「満15歳になった年の3月31日」までは働いてはいけないと定められており、通常中学校卒業まではバイトは禁止されています。
ただし、例外的に許可された軽易な業務、たとえば 新聞配達や牛乳配達、子役・キッズモデルなどは、所轄の労働基準監督署の許可を得て条件を満たせば可能とされています。
このようなバイトは珍しいですが、実現できれば月に1万円〜3万円程度稼ぐ実例も報告されています。ただし、学校の時間外・保護者の同意・行政の許可などが必要であり、現実的な選択肢としては十分に検討したうえで判断すべきです。
親に不安視される理由とは
親御さんが「中学生がゲーミングPCを使いたがるとき」、なんとなく心配する気持ち、実は科学的な根拠や研究にも裏付けられているんです。やさしく解説しますね。
① 過度な画面時間による健康・睡眠への影響
日本での研究でも、子どもの長時間のスクリーン時間(ゲーム含む)は、肥満リスクや睡眠の質の低下と関連していることが明らかになっています 。
とくに「夜更かし→眠りにくい」というパターンは、ゲーム好きの中学生にはよくある話です。
② 学業・成績との関係への懸念
世界的な研究レビューでは、問題的なゲーム使用(過度に長時間・強い依存傾向)は、学業成績の低下と関連するケースが24件中大多数(24研究)で確認されており 、実際に30時間以上のオンラインゲームが累積GPAの低下と結びつくという報告もあります。
特に高校進学や受験のことを考えると、親としては目を光らせずにはいられませんよね。
③ ゲーム内容(暴力表現など)への懸念
日本の調査によると、デジタルゲームに対して親の約70%が「暴力シーン」「性的表現」「不適切な言葉遣い」などのコンテンツに不安を感じていることが分かっています 。
年齢に合わないゲームによる心への影響を心配する声は、多くの家庭で根強いものです。
④ 情報環境や依存のリスク
「ゲーム脳」論のような科学的議論もメディアや文化の中で話題となり、ゲームを長時間することによる集中力低下や感情コントロールの問題を懸念する親は少なくありません
根拠の多少は別として、こうした“科学っぽい言説”が不安を加速させることもあります。
中学生のゲーミングpcのお金を自分で用意する方法と親の説得術
親に反対されることも多いゲーミングPCの購入。ここでは、中学生でも実行できるお金の貯め方と、親を説得するコツを具体的に紹介します。
- お金の貯め方アイデア|無理なくコツコツためるには
- 中学生が親を説得するには?納得してもらえる伝え方のコツ
- ゲームだけではなくプログラミングも並行して学ぶという説得も
- よくある質問【Q&A形式】
お金の貯め方アイデア|無理なくコツコツためるには
中学生でも「ゲーミングPCを自腹で買いたい!」って思ったら、できることから地道に始めるのが成功のコツです。
特に便利なのが、毎日少しずつお金を増やせるポイ活アプリなどの活用です。一緒に見ていきましょう。
① 普通のお小遣いを「先取り」して貯金
中学生のお小遣いは月平均約2,500円~3,400円。その中から500~1,000円を先に貯金用に取り分けておくことで、自然と貯まる習慣がつきます。
② お年玉や臨時のお祝いもチャンスに
お年玉の平均額は約27,500円。これをそのまま使うのではなく、「貯金用」に分けるのも賢い方法。まとまった金額が一気に貯まるチャンスです。
③ ポイ活アプリで隙間時間にポイント稼ぎ
スマホが使えるなら、ポイ活アプリもおすすめです。アンケートや移動、ゲームなどでコツコツ稼げる仕組みで、貯めたポイントは現金や電子マネー、ギフト券に交換可能です。
- おすすめアプリ:モッピー、ワラウ、ポイントインカム、ちょびリッチなど。中学生でも取り組みやすく、交換先や使いやすさにも定評があります。
- 移動するだけで貯まるアプリ:Powl(ポール)、aruku&(あるくと)は、歩数や簡単なアンケートでポイントが貯まり、50円〜から交換可で使いやすいです。
④ アンケートモニターや安全な副業でプラスに
空き時間でできるアンケートモニターは、中学生でも気軽に始められる手段。例えばマクロミルなど、信頼性の高いサービスなら安心して参加できます。
また、フリマアプリで不要品を販売したり、家で親の手伝いをして“お手伝い報酬”をもらうなど、リアルな手段も有効です。
中学生が親を説得するには?納得してもらえる伝え方のコツ

親を説得するには、ゲームだけでなく「学びや成長のための投資」という視点を明確に示すことがカギです。
ただ欲しいと頼むのではなく、「PCを組むことで得られるスキル」や「家庭へのメリット」などを丁寧に伝えていきましょう。
- 「自作することで学びになる」と説明する
パーツ選びから組み立てまでを経験すると、パソコンの仕組みへの理解が深まり、将来的なプログラミングやデジタル創作などにも役立つスキルが身につくことを伝えましょう。
これは単なるゲーム目的より、将来の自己投資としての説得材料になります 。 - 使用ルールを具体的に約束する
親が不安に思うのはゲームによる時間の無駄や課金などの心配も大きいです。そこで「1日の使用時間を決める」「夜9時以降は使わない」「勉強や家庭の手伝いを優先する」など、ルールを自分から提案して了承を得るのは効果的です 。 - 責任感を示すための具体的な提案
Yahoo!知恵袋の事例では、「高校生になったらバイトして返す」「お年玉は全部渡す」「成績が400点以下になったらPC没収」など、責任を明文化した提案が親の安心を引き出したという意見もあります 。 - 情報収集とプレゼンを通じた準備の丁寧さ
自分なりに調べて、例えばPCのスペックや予算、使用目的、ゲームだけではない活用などをまとめて、パワポや紙で資料を作成して話す姿勢が「ちゃんと考えている」という印象になります。
このアプローチは説得力が大きく増す方法です 。
ゲームだけではなくプログラミングも並行して学ぶという説得も
日本では2020年から小中学校でプログラミング教育が必修になっていて、プログラミングって珍しいものじゃなくなってるんです。
これは、学校教育として「論理的な考え方」「問題を分解する力(コンピュータ思考)」などを育てる重要な学びだからという理由もあるんですよ 。
さらに、世界的にも「プログラミングって読み書きそろばんと同じくらい今の世の中に必要なリテラシーだ」って声があって、単なる学びじゃなくて 社会や将来に直結した力を育てる正真正銘の教育として注目されてるんです。
親にこう伝えてみては?
「ねえ、ただゲームをやりたいだけじゃなくて、プログラミングも一緒に学んでみたいんだ。たとえば、ゲームの仕組みを理解するためにコードをちょっとずつ書いてみるとか、Scratch(スクラッチ)で簡単なゲームを作ってみるとか、そういう風に遊びと学びを組み合わせたいんだよね。」
って言うと、「ただ遊んでるんじゃないね」って伝わりやすいと思います。
プログラミングは、論理的に考える力や問題解決の考え方が自動で鍛えられるから、「ただの遊び」じゃなく「未来へのスキルアップ」につながるって印象、すごくいいですよね。
こんな言い方も効果的かも!
- 「学校でもプログラミング教育が始まってるし、僕(私)もその流れに乗ってみたいんだ」
- 「ゲームの好きなところだけじゃなくて、『どう動いてるのか』を理解できたら楽しさもすごく深まる気がする」
- 「将来パソコンに強くなりたいから、その第一歩として触ってみたいんだ」
論理的な裏付けと、未来に向けた学びの姿勢を示せば、親も安心しやすいですよね。
このスタンスだと、ただ「欲しい!」と言うよりも、「学びにもつなげたい」という前向きな姿勢が伝わって、親の心もグッと開いてもらえる気がします。ぜひ参考にしてみてくださいね!
よくある質問【Q&A形式】
- 中学生がゲーミングPCを欲しいと言うと、親はなぜ反対するの?
-
ゲーミングPCの購入で約16万円は大きな出費ですし、親御さんは金銭的な負担だけでなく、「ゲームの依存」「学業への影響」「課金トラブル」など多方面から心配されることが多いようです
- ゲーミングPCって、本当に必要なの?
-
ゲーム専用機(PS4やSwitchなど)でも楽しめますし、費用効果を考えると「今は不要」と言う意見もあります。実際、ある中学生は「プログラミングや記事を書くだけなら安価なPCで十分」と考えることもあります
- 中学生でも自作PCってできるの?
-
実際に「中学生が自作PCを組んだ」事例も報告されていますが、親に納得してもらうために「自作は学びや技術を得る経験になる」と説明したという例があります
まとめ 中学生のゲーミングpcのお金
ここまでの内容を簡単にまとめると、「中学生がゲーミングPCを買う」っていう話は、夢物語じゃなくて案外現実的なんだなって感じました。
ただ、お金の面や親の理解っていうハードルがあるのもたしかで、そこをどう乗り越えるかがポイントになってきます。
コツコツ貯めたり、ちゃんと理由を伝えたりすれば、思ってるより前に進めるかもしれません。
ポイントを絞ると以下の通りです:
- ゲーミングPCは安くても10万円台、必要な周辺機器も含めると20万円近くかかる
- 中学生の平均お小遣いは月2,500円〜3,400円、計画的に貯めることがカギ
- バイトは禁止だけど、お年玉や親からの支援、ポイ活アプリも活用できる
- 親に「学びとしての活用」や「ルールを守る姿勢」を伝えるのが説得のコツ
- ゲームだけでなく、プログラミングにも挑戦する意欲が信頼につながる
個人的には、プログラミングを一緒に始めてみたことで、「遊ぶだけじゃないんだな」って親に伝わったのが大きかったです。
「ただ欲しい」じゃなくて、「何に使いたいのか」を自分の言葉で話せると、ちゃんと伝わるんじゃないかなって思います。
参照元:
- 金融広報中央委員会|https://www.shiruporuto.jp
- 総務省統計局|https://www.stat.go.jp
- 労働基準法(e-Gov法令検索)|https://elaws.e-gov.go.jp
- モッピー公式サイト|https://pc.moppy.jp
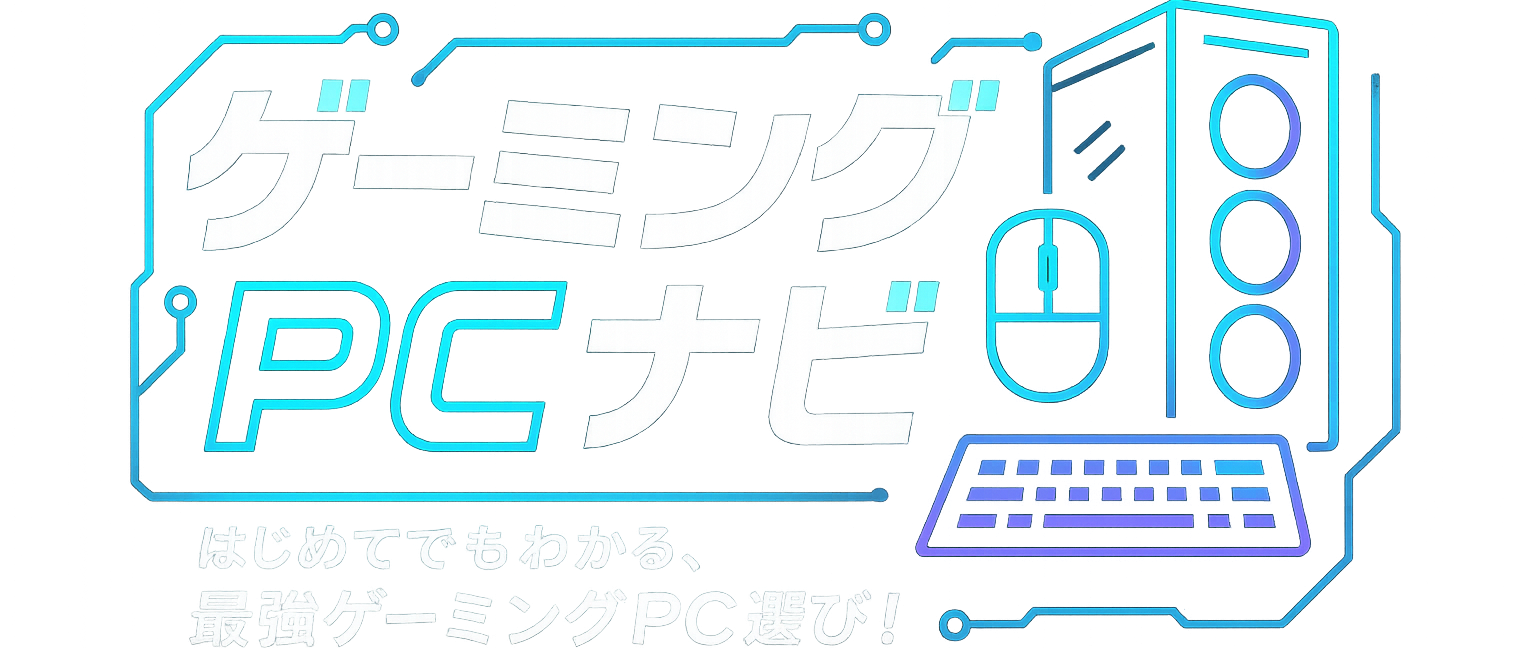

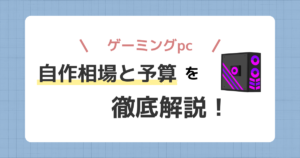

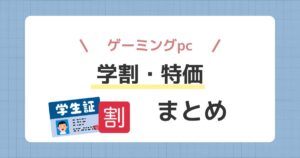



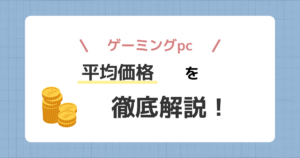

コメント